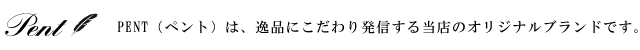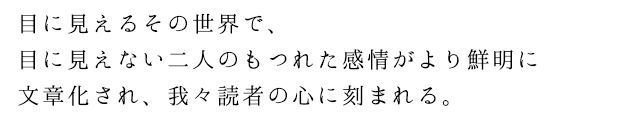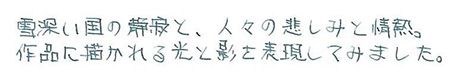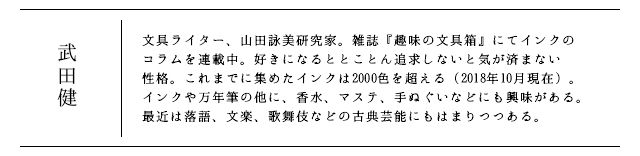川端康成は、個人的に父の関係で家族ぐるみの付き合いをしていたこともあり、何かと思い出の多い作家のひとりである。
とはいうものの、ぼくが4歳の時に亡くなったので、ぼくの記憶の中の川端康成は本当におぼろげなものだ。
ただ、唯一覚えているのは、タバコの匂い。
川端先生はヘビースモーカーで、当時は父も同じようにタバコを吸っていたので、二人が一緒にいるといつも部屋はタバコの煙が充満していた。
そして、川端先生はぼくのことを孫のように可愛がってくださっていたので、お会いするたびに抱っこされるのが常だったらしい。
そして、いつも着物姿の先生の着物からはそのタバコの香りが良く漂っていたのだ。着物の独特の肌触りと、タバコの香り。ぼくがなぜこんなに強烈にこのことを覚えているのかというと、そのような記憶をぼくに残した人は他にいないからだ。父は着物を着ることは一度もなかったし、他の人はそこまでタバコを吸うことはなかった。だから、着物とタバコの記憶は明らかにぼくにとっての川端康成の記憶と直結するわけだ。
しかし、当然のことながら、ぼくはまだ当時は文字すらも読めない子どもだったことが悔やまれる。
なぜなら、大人になってから、すっかりぼくは彼の作品の虜になってしまったから。

最初に読んだ作品は、小学生の時に教科書に載っていた「バッタと鈴虫」だ。幻想的な物語で、どこか郷愁を覚える作品だったのをよく覚えている。子ども心に、どこかエロティシズムを感じさせる場面もあり、うすうす、川端作品全体に漂うどこかエロティックな部分を本能的に察知してもいたような気がする。
本格的に川端作品を読むようになったのは高校に入ってからのような気がする。
大好きだった三島由紀夫のことを川端康成が高く評価していたという話も聞いていたから、じゃあ、きっと川端作品もぼくは理解できるだろうと勝手に思って読み始めたのである。
もちろん、三島と川端は違う部分も多いけれども、やはりぼくの中では似たようなカテゴリーに入り、それは、実は谷崎にも通じるものがある。
この3人に共通しているのは、ザ・変態。ノーベル文学賞作家に対して「変態」なんて言うと怒られるかもしれないけれども、でも、文学というのはもともと変態を描いたものだとぼくは思っているので、これは最高の賛辞なのである。
川端康成の変態というのは、これがまた少し独特で、一見、変態に見えないのだ。作品も深く深く読んでいけばいくほど、不気味な気持ちになる。
映画化もされたし、教科書にもしばしば取り上げられる「伊豆の踊子」や「古都」にしても、普通の物語として多くの人の心に残る作品ではあるけれども、良く読むと、どこか普通の人とは違うアブノーマルな世界がひっそりと隠れていることに気づく人は気づくだろう。その暗号めいた世界がぼくにはたまらない。
中でもその変態性を感じるのが「眠れる美女」という作品。「横になっている少女に決してお手を触れになりませんように」と旅館の女将に言われ、それを必死に抑えながら少女の横に添い寝する老人。もう、そのシチュエーションだけで十分変態ではないですか!
実は本当はその作品を色にしたかったのだが、あまりにもいびつでこれは色にするのは難しいのではないかと思い、この作品を色彩化することは断念した。
そこでぼくが今回のシリーズで採用したのが「雪国」である。
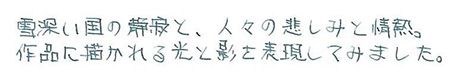
この作品は冒頭の一文が非常に有名だが、そこから続く雪国の駅の描写は深く印象に残るし、その後の登場人物たちの心情も静かに胸に刻まれる。
そして、その舞台となるのは、新潟の雪深い温泉町。淡々としたつきあい方しかしない男と、それに対して激しい情熱を抱く芸者の二人の心の対比は、雪国という淡色の世界だからこそ、よりくっきりと描かれるのではないだろうか。
雪国には色彩が少ない。雪に埋もれた白銀の世界だ。目に見えるその世界で、目に見えない二人のもつれた感情がより鮮明に文章化され、我々読者の心に刻まれる。
決して長くはないこの作品が長く愛されているのは、そういう小説の醍醐味を感じるからなのではないだろうか。
そんな世界観をぼくはどのように色彩化しようかと少し悩んだ。なぜなら、本当の意味での白銀の世界というのは万年筆インクで表現することは難しいからだ。
しかし、雪国というのは必ずしも白一色ではない。どこか墨絵のような色もうっすらと残っている。そこでぼくが考えたのがブルーグレーだ。薄めの青灰色は、雪国の朝や宵闇迫る時間帯の空気感にも通じる。
ぜひ、このインクでこの作品で描かれている独特の世界観を感じてもらえたら嬉しい。