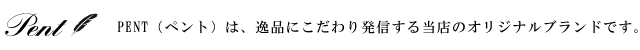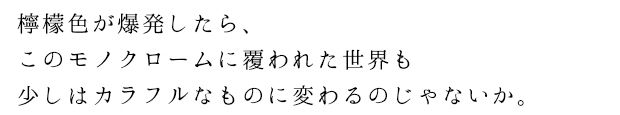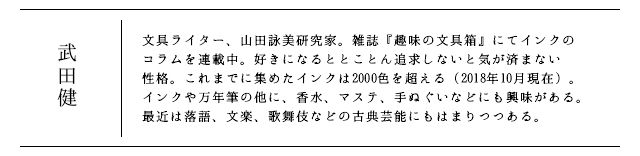「檸檬」という作品を初めて知ったのは、実は文学作品ではない。とある男性シンガーソングライターの曲の中にこの「檸檬」をモチーフにした曲があり、そこで初めてこの作品のことを知ったのだ。
檸檬と聞くと、多くの人はあの鮮やかな黄色を思い出すだろう。明るくて、みずみずしい色彩とともに、思い出されるのがすっぱい味。思わず口をすぼめたくなるような効果が檸檬という果実にはある。
しかし、梶井基次郎の描いた「檸檬」の面白いところは、その果物としてのイメージだけではなく、そこにさらに手榴弾の形を重ね合わせているところであろう。あの檸檬の形はまさに手榴弾のようではあるが、その二つを結び付ける人はなかなかいないのではないだろうか。そして、それが見事に作品とシンクロするところもこの「檸檬」の魅力だと思う。
檸檬を手榴弾に見立てて、さらにそれを自分の鬱々とした気持ちを吹き飛ばすことに使いたいと妄想するストーリーは、どこか現代人にも通じるものがあるのではないだろうか。
そういうちょっとした、そして誰にも迷惑をかけないいたずらを妄想することは楽しいし、ひと時の慰みにもなるだろう。それを文学作品として今でも共感を得られるというのは、そこに普遍的なものがあるからなのではないかとぼくは思っている。
作品そのものは短編小説なので、手軽に読むことができるが、その短い物語の中にちりばめられているのは、心象風景と色の対比である。様々な憂鬱になる出来事に囲まれていると、目に見える世界も色あせて、時にはモノクロ―ムのように見えてしまうこともあるだろう。だが、そこに、「檸檬」という強烈な黄色をもった果実が加わることによって、そこだけが色鮮やかに、くっきりと見えることがある。それは、憂鬱が影を濃くすればするほど、その箇所だけが明るく光るのだ。

この作品が発表されたのは、大正14年、1925年のことである。今から90年以上前のこと。当時と今ではもちろん、我々日本人を取り巻く状況はまったく変わってしまったし、社会的情勢もまったく異なる。しかし、この作品が今でもしばしば文学好きのみならず、様々な場面において何かと引き合いに出されるのには、何か大きな理由があるのではないかと思う。
もちろん、作品の中に、我々文具好きにはなじみの文具書店が登場する、ということも作品自体に親しみを感じる一つの要因であるわけだけれども。

内容的な部分ではもちろん、いろいろと変容しているところはあるけれども、90年以上たった今でも、世の中というのは、陰々滅滅とした出来事であふれている。それは、個人的なことであるかもしれないし、あるいは一向に改善されず、ますます複雑化して、疲弊しきっている現代社会そのものであることも少なくないだろう。
そんな中でこの作品を読むと、3時代前に書かれたものであったとしても、「わかるわかる!」となり、自分も檸檬色の手榴弾をしかけたい気持ちになってしまうのだ。もし、その檸檬色が爆発したら、このモノクロームに覆われた世界も少しはカラフルなものに変わるのじゃないかという希望的妄想も生まれる。
そんな檸檬をインクの色で再現したいと思った時、ぼくがまっさきに考えたのは、本物の檸檬の色とは違うものにしようということだ。この作品に漂う、何ともやり切れない自分を取り巻く環境に対する陰鬱とした気持ちもこのインクに閉じ込めたいと思った。そこで生まれたのが、少し暗いレモン色だ。酸っぱさの中にある悲しさを色に閉じ込めてみた。ぜひ、その対比をこの色から感じ取っていただきたい。